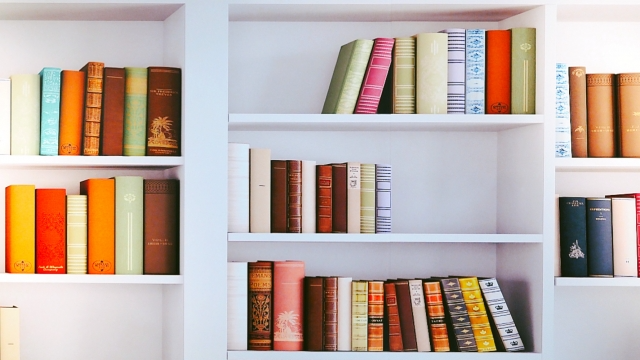「受け身の読書」→「攻めの読書」で人生を変える!!!
こんにちは、実家に帰って田舎生活のsurveyPです。
本日は赤羽雄二著「1日30分でも自分を変える"行動読書"『ACTION READING』」です。
ちょっと汚れてますが、これは本を読むのが遅い私のせいなのでお気になさらず。(スマヌスマヌ)
今回はこのブログに目次を付けていこうと思います。
読むべきかどうか、だけを見る人は5.感想まで飛んでください!!
---------------------------------------------------------------------------------
- 書籍の目次。
- 筆者の紹介
- 書籍の概要
- 気になったワード
- 個人的感想
---------------------------------------------------------------------------------
では参りましょう!!!
1.目次
序章:「読みたくても本が読めない」5つの理由
第1章:なぜ、できる人は忙しくても本を読むのか
第2章:できる人は忙しくても、なぜ、本が読めるのか
第3章:短い時間で、読んだ内容を身につける「集中読書術」
第4章:できる人は読んだ本をどう活かすか
第5章:無駄な本で時間を費やさないために
となっております。ここのところ目次まとめをしていると、人によっては目次だけでこの章読みたいなみたいなのがあったりなかったりするのも続けて本を読んでいるから気づけたことかもしれませんね。
2.筆者の紹介
筆者、「赤羽雄二」は小学校高学年から、読書通で1800冊ほどおよそ40歳までに読んでいるそうです。東京大学工学部を卒業後は小松製作所にて設計・開発。後にスタンフォード大学に留学し終始上級課程を卒業、マッキンゼーに入社しました。そこでは、経営コンサルタントとして、よりいろいろなジャンルの本を読む必要性が高まり、コンサルタントする顧客の業種に合わせて、関係書籍を10~20冊を数日間の間に読んでしまうそうです。この時点で私surveyPとはとは違うなあと思います。(本ブログで読み始めたくらいwww)
3.書籍の概要
序章では何が原因で本を読めないのかを説明されています。
総括すると、「忙しい」や「気になることがあって集中して読めない」。つまり読書に対して「受け身」であることが指摘されています。改善するには自分から効果的な読書方法、「攻めの読書」にシフトする必要があります。
1章では
読書のメリットについて、筆者の実体験とともに記述されています。筆者自身、前述したように、読書家で、それによって仕事や人間関係をうまくこなしていたことがわかります。それだけ読書とは尊いのです。
2章では筆者のように忙しい人が週に最低1冊、仕事だと数日の間に10~20冊一気に読破しているのか説明しています。筆者の1日は7時に起床し、19時半まで会食や、講演をしています。普通のサラリーマンより忙しい生活をしていると思います。それでも毎週1冊は本を読んでいます。その方法を記述されています。
本を読めていない人は読書の時間を重要だと、価値が高いものだと認識していないのです。だからこそ読書の時間に「市民権」を与え読書の時間を1日30分でもいいので作る必要があります。例えば、夜、家帰って寝る前や、食事をしたあと、入浴後など、自分の決めた、そして無理のないような読書を心がけるとだんだんと習慣となっていき読書が続きます。スケジュール帳に読書の時間を書き入れるのもいいと思います。とにかく一日の予定に読書の時間を組み込むのです。
3章では短い時間でも読んで内容を身につける読書術について語られています。次の3点が特にインプットするテクニックです。
・重要なところやオモシロイと思ったフレーズなど気になるところに蛍光ペン
・読破した直後に書いてあったことが出てこなくなるまでメモり続ける(ただし、読み返さない)
・「なぜこの本を手にとったのか」を意識する。
この3点は重要と思います。他にも紹介されています。
4章では「攻めの読書」の真骨頂、読んだ本をどう活かすかについてです。ブログに書く、人に話す。「チャレンジシート」に書いて、宣言し、実効する。
「チャレンジシート」とは筆者が独自に作成した、ツールです。これを書くことによって、何を得たか、何を目標にするかが明確になり、積極的なアウトプットに繋ががります。ぜひ、サイトを利用してみてください。
5章では自分としては以外だったのですが、無駄本をしないための方法が記してあります。そもそも読書量の目標として30代までに300冊と筆者は論じています。その先は無駄な本を読まないために、世の中の問題や、課題などを見つけたり、展示会に行って疑問に思ったことなどを仮説を立て、考えること、そして、それを改善していくことが重要です。ここでは、ネット記事についても書かれています。筆者はgoogleアラートを用いて記事を探しています。これはとても便利で、自分が設定したネットの記事を指定した時間にまとめて通知してくれるものです。ちょっと使ってみましたが便利ですねこれ!!
4.個人的に気になったワード
結構3.の概要で言ってしまったんですが、2つほど。
1つ目は会食や講演会に行くとき、その人の出している本やブログは一読している、マナーとしてと言われたのが驚きでした。今まで自分は読めばいいかなくらいに思ってました。つまり、「人よりプラスでしょ、俺偉いでしょ」位の感覚です。それを筆者はマナーと言っているのです。これを繰り返せば、知識も増えるし、相手に対して、質問できるし、もしかしたら、人脈として使えるレベルになるかもしれない。そう思いました。なにげないワンフレーズだったのですが、自分としては考えを変えるきっかけとなりました。
もう一つは「読む本の半分は小説を読め」です。実用書、専門書だけでもいいのかなと思っていた自分にとっては後ろ指を刺された気持ちです。小説を読む理由としては、ざっくりと、人の気持ちがわかる、やる気が出る、といったところです。いわゆる小中高の国語の問題ですよwww。しかし1800冊以上を読破した筆者が自分の体験談とともに言っているので間違いないのだと思います。これからは楽しみにふけようと思います。
5.感想
正直に言います。筆者、赤羽さんには申し訳ないですが、科学的根拠を示すタイプではなく、自分の経験ベースだったので、ややメンタリストDaiGo教の自分には刺さるものが少なかったように感じます。また今度紹介しますがメンタリストDaiGo著「知識を操る超読書術」では科学的根拠をもとにどう読めば効率的に本を読めるかということが書いてあります。自分としては、Daigoの本と比べるとちょっと弱いかなと思いました。なんせ自分は理系人間になってしまったもんで、、 逆に経験ベースの方が重要だと言う方が読む場合にはDaigoの数字で語られるより説得力はあると思います。私の場合は、このように感じてしまったのは先にDaigoの本を読んでしまったってのが大きいと思います。しかし、チャレンジシートは未来を作る上でとてもいいツールと思いました。少し調べてみると、実際にやっている人がブログ等で上げているのが見られます。
この本は人は誰かの経験に基づいたほうが現実味があって、飲み込める、なんかの研究やデータ、専門的な用語みたいな物々しいものが苦手で、読書を効率的に、読みたいという方に特にオススメです。